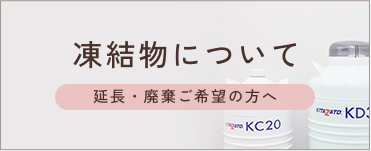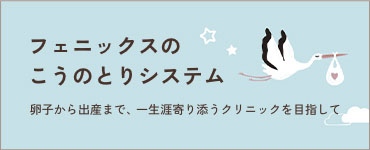「不育症」という病気を、聞いたことがありますか?
妊娠後子宮内で育ちにくくなる病態、不育症

「不育症」は「不妊症」とは違い、妊娠が成立しても、流産や胎児が子宮内で成長しにくくなる病態を指します。以前は、習慣流産とも呼ばれており、日本不育症学会は、「流産あるいは死産が2回以上ある状態(生児獲得の有無は問わず、流産または死産は連続していなくてもよい)」と定義しています。
流産は妊娠中に最も多く見られる合併症であり、約15%の割合で発生します。そのうちの90%以上が妊娠10週未満の初期に起こります。自然妊娠で起こることも多く、不妊治療をしている方に限りません。実は「よくあること」なのです。しかし、あまり語られないためそれが一般的に知られていないのが現実です。多くの方は、流産してしまった時には「どうして私が?」と驚き、妊娠の喜びから一転深い悲しみに突き落とされたように感じてしまいます。
また、流産の約80%は胎児の染色体異常が原因で起こります。決して、女性の不摂生や過失・ストレスで流産が起こるわけではありません。それにもかかわらず、流産を経験された患者さんは、自分の行動を責めてしまいがちで、自尊心の低下を感じることがあります。また、中には抑うつや不安障害を発症する方もいらっしゃいます。流産を二度三度と繰り返すことで、絶望感を抱き、赤ちゃんを望んでいても妊娠すること自体が怖くなってしまう方もいます。そのため、不育症の治療には精神的な支援が欠かせないとされています。
不育症が起こる大きな原因
不育症はつぎの4つが大きな原因とされています。①抗リン脂質抗体症候群 ②先天性性子宮形態異常 ③胎児染色体異数性 ④カップルの染色体異常です。他にも内分泌異常(糖尿病や甲状腺機能低下症)や自己免疫疾患も影響します。
①および②については、採血や超音波検査・子宮鏡検査を行なって診断し、必要と判断された場合には、低用量アスピリン・未分画ヘパリン療法や子宮の手術が治療の選択肢となります。③の胎児染色体異数性に伴う流産に対して、体外受精治療においては、いわゆる着床前診断で流産が予防できる効果が認められています。着床前染色体異数性検査preimplantation genetic testing for aneuploidy (PGT-A)が、日本では2014年から特別臨床研究としてスタートしていて、当クリニックでは2022年より施設認可を受けて検査を開始いたしました。④のカップルの染色体異常に伴う流産に対しては、着床前構造異常検査PGT-SRが適応となります。
このように不育症の治療は多岐にわたり、女性の年齢および卵巣機能に応じて不妊治療と並行して行う場合もあります。また、医学的な見解をさらに深めるために、不育症の専門施設と連携して診療を進めることもあります。
一人で抱え込まず相談してください

不育症と診断されても、その後8割の方が元気な赤ちゃんを迎えられると言われています。しかし、流産や死産を繰り返すことは、精神的にも大きなダメージを残し、その心の傷が癒えるのにはとても時間がかかってしまうのも事実です。不育症のリスク因子に対する適切な検査や治療を進めると同時に、パートナーや医療者と共に心のケアを大切にし、治療と向き合うことが非常に重要です。
もしも、あなた自身または周囲の方に、流産に対するご不安や辛い気持ちを持った方がいらっしゃいましたら、一人で抱え込まずフェニックス アート クリニックまたは同法人のフェニックス メディカル クリニック産婦人科へ、どうぞお気軽にご相談ください。
フェニックス アート クリニック
副院長 医師 金谷 真由子