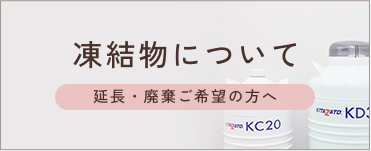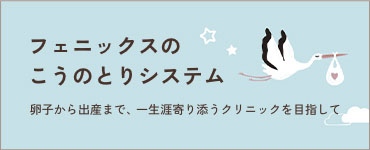保険診療をご希望の方
support
フェニックスアートクリニックは
保険診療認定施設です
2022年4月からの不妊治療の保険適用開始に伴い、当院でも保険診療を実施しています。保険適用の年齢や、体外受精、顕微授精、胚移植、融解胚移植の回数制限などありますので、詳しくは下記を参照ください。また、基本となる保険診療の情報は厚生労働省のサイトよりご確認ください。
初回診療について
初回診療時は、保険診療・自費診療、共に自費となります。当院では十分に医師と相談し、患者さんにとって一番納得いただいた上で治療を開始させていただくため、自費診療にてしっかりご相談のお時間をとっております。その際、保険での治療を希望された方は、2回目より保険診療が開始となります。
一般不妊治療(人工授精・一部タイミング療法※ ・ 一般不妊検査)
初診にて保険診療を希望された方は、2回目の受診日より「一般不妊治療計画」を作成し、保険診療が開始(初診)となります。
※当院は高度生殖補助医療をメインとして行っております。ステップアップを視野に治療されている中で一部タイミング療法を行う場合がございます。
高度生殖補助医療
初診にて保険診療を希望された方は、2回目の受診日より「生殖補助医療治療計画書」を作成し、保険診療が開始(初診)となります。
※初回の計画作成の際はご夫婦での来院をお願いしております。
保険診療に際してのご案内
保険適用の年齢
-
タイミング療法、
人工授精回数制限なし
-
体外受精、顕微授精、
胚移植、融解胚移植年齢制限、
回数制限あり※治療計画書作成日
において43歳未満
保険適用での体外受精、顕微授精、胚移植、融解胚移植の回数制限
保険適用になった初めての胚移植術に係る治療計画を作成した日における年齢で、胚移植回数が決定します。保険診療における回数制限の回数は胚移植の回数です。採卵回数はカウントに入りません。
-
初回作成日が
40歳未満胚移植回数
6回 -
初回作成日が
40歳以上43歳未満胚移植回数
3回
ただし、胚移植の回数制限を超えた場合は、年齢に関わらず保険適用の治療計画は作成できません。ご自身での「胚移植回数の正確な管理」が必須になります。回数制限についての虚偽申告や思い違いによる誤りがあった場合には、後ほど当院規定の自費診療の算定を自己負担でお支払いしていただく必要が生じます。
- ※当院に転院してくる場合でも前の治療施設での保険診療の胚移植回数の報告が今後必須となります。
- ※胚移植により妊娠し出産した後に、次の児の妊娠を目的とした場合はその治療開始日の年齢で新たに胚移植回数が決定します。
ご夫婦での治療について
カップル確認書類について

保険診療での治療には婚姻関係の確認が必須となりました。これに伴い、治療に入る前に下記書類を確認させていただくこととなりました。こちらを確認できない場合、保険、自費関わらず治療周期に進めませんのであらかじめご準備の上ご対応ください。
なお、婚姻関係の確認に関しては、どの治療(タイミング、人工授精、体外受精、胚移植)においても必要です。
-
確認書類(保険診療実施時に必須)
発行日から3か月以内の公的書類
①婚姻関係のあるカップル(入籍済みの方):戸籍謄本(1回ご提出)※返却します。
②事実婚のカップル:個々の戸籍抄本もしくは独身証明書(年に1回ご提出が必要です)事実婚を含む未入籍の場合、治療中に書類の発行日から1年経過する場合は再度書類の提出が必要です。
-
提出書類(治療周期に入る際に必須)
当院規定の婚姻関係等申告書
ご夫婦(パートナーと一緒に)で治療計画を作成する際に医師の説明のもとその場でサインを頂きます。自費での診療を希望される場合も、ご提出をお願いします。
保険診療の場合は確認書類、提出書類の両方が確認でき、次項記載の管理計画書をご夫婦と作成後、治療開始となります。
ご夫婦の治療計画について
保険診療での治療を開始する際は医師が作成した治療計画書を説明し、ご夫婦に同意いただく必要があります。初回治療計画作成日は、ご夫婦での来院が必須となります。治療計画作成日とは、(タイミング療法、人工授精)体外受精の治療を始めるにあたり、医師と今後の治療計画を立てていただく日になります。治療計画の見直しの際には、再度ご夫婦での来院が原則必須となります。
予約方法
-
希望する治療周期の前の周期
- 治療計画が夫婦で立てられない場合は、保険での治療開始ができません。
- 治療計画書作成内容が変更になる場合、ご夫婦の来院が必要です。
-
【治療計画書作成】でご予約ください。
- ご夫婦で必ずご来院ください。
- 採卵や移植に必要な感染症採血、術前採血などを採血させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
診療について
保険適用の薬について
保険診療で治療を行う場合は注射薬、内服薬に関しても一部保険適用となりますが、決められたお薬の種類、投与量、日数など制限がございます。
いままで自費で使用していた薬が保険適用外の場合は、使用することができません。
先進医療について
先進医療とは本来自費診療のため、保険診療と併用できない医療を「先進医療」という枠組みを作り、保険外併用できると厚生労働省が決定したものをいいます。併用できる医療の内容は厚生労働省によって決められています。
当院で対応できる先進医療
- PICSI
- IMSI
- 膜構造を用いた生物学的精子選択術(マイクロ流体技術を用いた生理学的精子選択術:ZyMot)
- SEET法
- タイムラプス
- 子宮内膜スクラッチ
- ERA
- EMMA、ALICE(子宮内膜フローラ検査)
- 選定医療

選定医療について
精子凍結が選定医療になりました。
医師が必要と判断した場合、保険診療と併用できます。
詳しくは診察にてご相談ください。
保険適用にならない治療
- PFC-FD作成、注入
- RIF検査(VitD採血、免疫バランス検査、Vorinosフローラ検査、慢性子宮内膜炎検査)
- 連続採卵(1周期に2回採卵)
- 貯卵(採卵して受精卵を獲得した後、移植せずに再度採卵をすること)
- PGT-A【着床前診断】(先進医療Bに申請中。厚生労働省より施設認定された施設のみ先進医療として実施できる可能性がある)
- ※社会的理由での採卵、移植、卵子凍結、医学的理由の精子、卵子凍結はすべて保険適用とはなりません。
保険適用にならない薬剤
採卵周期
排卵予防のために使用する:マーベロン、レルミナ
採卵決定時の尿検査
卵胞発育を目的とするための薬剤:マーベロン、プレマリン
移植周期
子宮内膜が薄い、着床障害予防目的:バイアスピリン
着床障害予防目的:プログラフ、プレドニン
胚移植後の子宮収縮抑制剤:ダクチル、ブスコパンなど
ホルモン補充周期に使用している薬剤:バイアスピリン、ユベラ、スプレキュア、レルミナ
※その他保険適用にならない薬剤、治療もございます。また情報が今後更新される可能性もございます。
ご留意事項
保険と自費の混合診療について
保険での治療を行う場合は自費診療との併用、すなわち「混合診療」が厚生労働省や社会保険支払基金より禁止されております。
採卵、移植のために自費診療で行っていただく採血【感染症採血・術前採血】があります。こちらは保険診療が始まる前に自費にて実施していただいております。
またPGT-A/PGT-SRは自費診療でございます。保険診療で採卵した受精卵は、PGT-A/PGT-SRの対象外ですので、予めご了承ください。
他院より転院をご希望の患者さん
他院から転院をご希望の患者さんは、前医での診療が自費保険に関わらず、紹介状【保険で実施した胚移植の回数が明記されているもの】を、必ずご持参いただいております。
既往の保険診療での治療回数に虚偽がございますと、すべての診療を遡って全額自費診療にて請求させていただきます。 必ず、正しい申告を頂く必要がございますので、転院の際は、予め紹介状をご準備いただきますとよりスムーズに診療に移行できます。
※紹介状なく初診を受けていただくことは可能ですが、その際は紹介状のご提出が確認できるまで、治療開始できなくなってしまいますので、予めご承知おきください。
スケジュールの変更について
- 保険診療のスケジュールから自費診療のスケジュールへの切り替えはできません。
- 体外受精、顕微授精、胚移植の治療計画を決定した後に、自己都合により治療時期を延期する場合は、再度治療計画作成の診察に来院が必要になります。

凍結胚延長について
凍結胚延長を保険で行う場合は「医学的に妊娠前に治療など行う必要があり、受精卵を移植することができない、または医師より妊娠を延長するよう指示があった場合」のみです。
妊娠後の余剰胚の延長や自己都合での延長は自費での延長となります。
高額療養費について
保険診療での診療は高額療養費の適用となります。
【注意事項】 高額療養費での対象治療費は月ごとになります。月をまたぐと限度額に達せず請求できない場合がありますので、ご留意ください。
助成制度について
support
自治体ごとに独自の助成制度が提供されている場合があり、これらの制度を活用することで、治療費の一部を軽減することが可能です。
※当院は、東京都の特定不妊治療費助成事業の指定医療機関として、各助成制度をご利用いただけます。
東京都特定不妊治療費(先進医療)助成制度
この制度は、保険適用された体外受精および顕微授精の治療と併用して自費で実施される「先進医療」に係る費用の一部を助成するものです。
助成の対象となる条件
- 法律上の婚姻をしている夫婦または事実婚の要件を満たすこと
- 治療開始日から申請日まで東京都内に住所を有すること
- 治療開始日における妻の年齢が43歳未満であること
- 先進医療を実施する医療機関として登録された保険医療機関で治療を受けたこと
不妊検査等助成事業
この制度は、保険適用された体外受精および顕微授精の治療と併用して自費で実施される「先進医療」に係る費用の一部を助成するものです。
助成の対象となる条件
- 東京都に住民登録をしている婚姻または事実婚の夫婦であること
- 検査開始日における妻の年齢が40歳未満であること
- 助成対象期間内に保険医療機関において夫婦ともに助成対象の検査を受けていること
助成額
※詳しくは、東京都福祉局 「不妊検査等助成事業の概要」 をご確認ください。
卵子凍結に関わる費用の助成
東京都は「卵子凍結に係る費用への助成」制度を実施しています。この制度は、将来の妊娠に備えて卵子凍結を希望する女性を経済的に支援するものです。
対象者
東京都に住む18歳から39歳までの女性(採卵を実施した日における年齢)
助成額
- 1. 卵子凍結を実施した年度:上限 20 万円
- 2. 次年度以降:保管に係る調査に回答した際に、1年ごとに一律 2 万円(最大5年間、2028年度まで)
つまり、最大で 30 万円の助成を受けることができます。
対象要件
- 1. 都が開催する卵子凍結に係る費用の助成対象者向け説明会へ参加した後、調査事業への協力申請を行い、協力承認決定を受けること
- 2. 本人が説明会に参加した日から1年以内に、卵子凍結に係る医療行為を開始すること
- 3. 説明会への参加を申し込んだ日から未受精卵子の凍結が完了し、都へ申請する日までの間、継続して東京都の区域内に住民登録をしていること
- 4. 説明会へ参加した日以降に、登録医療機関において医療行為を開始すること
- 5. 排卵を実施した日における対象者の年齢が18歳以上40歳未満であること
- 6. 凍結卵子の売買、譲渡、その他第三者への提供を行わないこと。また、海外への移送は行わないこと
- 7. 凍結卵子を用いて生殖補助を実施する場合は、必ず夫(婚姻の届出をしていないが、事実上の婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の精子を使用すること
- 8. 卵子凍結後も都の実施する調査に対し、継続的に回答すること(調査は令和10年度まで実施)
- 9. 調査協力助成を受けようとする医療行為について、他の法令等の規定により、国又は地方公共団体の負担による医療に係る給付の対象とならないこと
注意点
この助成金は1人につき1回のみ受けられます。 申請期限は卵子凍結に係る医療行為が終了した日によって異なります。2024年4月1日以降に医療行為が終了した場合、申請期限は 2025 年 3 月 31 日(厳守)となります。
※詳しくは、東京都福祉局 「卵子凍結に係る費用の助成」 をご確認ください。
自治体の助成制度について
各自治体によって助成範囲が異なります。お住まいの自治体のホームページにてご確認ください。